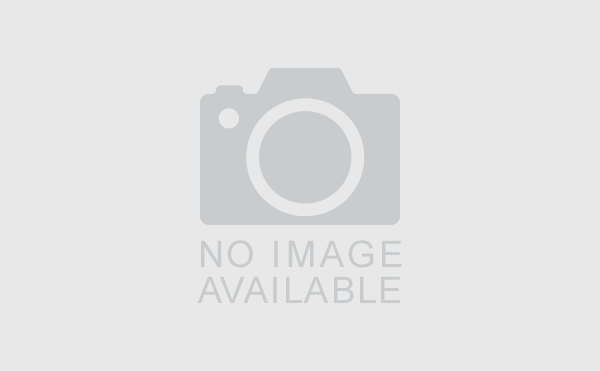Let’s proceed the road for business improvement.

IT技術の進歩と人々の関心、興味
 改善は、昨今のIT技術の進歩と人々の関心、興味から、”AI、RPA、DXを使って改善”をすべきと考えられています。
改善は、昨今のIT技術の進歩と人々の関心、興味から、”AI、RPA、DXを使って改善”をすべきと考えられています。
事務所の天井、作業現場の上空にドローンを飛ばし、帳票、PCアプリケーション、データーインプットの方法などの情報を収集し(社内許可を得て)、その情報を活用しデーターセンターで改善のプログラムを作成する。あとはそのアプリケーションを使うだけ?
At our company, we oppose unreasonableness wastefulness, and inconsistency. We use Best Practice to ensure our workplace is safe and do work correctly, speedy, easily and friendly. ”。うちの会社は、ムダ、ムラ、ムリを「3ムダラリ」、ムダ取に熱心だよ”、や ”他社の優良慣行を採用すれば、らくだよ”
業務は、多くの「情報」を収集し、加工し、伝達します。AI、RPA、DX、などの開発を自分達で手掛けるのではなく、情報システム部門と外部会社が主体のシステム導入が多い。多くの組織は完全なシステム導入はまだまだで、社のシステム統合には、まだまだ。きっとこの先も外部委託に多額の投資と時間が必要です。しかし、多額の費用と時間をかけても、実務担当者は「システムのコンサルに伝えたんだけど、いまいち伝えた点が反映されてない」、「かゆいところに手は届かずだよ」、「でも、まあいいとするか」、「不満なところあるけど、今までよりいいね、」、でも、微妙なこんなところを改善することが大事です。
大きな投資なく、改善を身近でする取り組みの方が、実務担当にとって「業務をやりやすくする」、「効率的なやり方にする」となります。このような取組みが、働きやすい職場づくり、仕事のやりがいにもつながりになり、さらにチームの自信のアップになります。改善後にはチーム肌感覚、皮膚感覚のあるシステムとなります。業務改善に取り組もうと考えたら、業務改善を難しく考えず、小さいことから何でも試してみることがポイントです。「気になっていること」、「改善したいと思っていること」、例えば、「何人もの人がいつも繰り返している作業の改善」、などから取組み始めることも必要です。
改善に慣れてきたら、手法やノウハウをまとめ、その手法·ノウハウを標準化してシステムに取りこんでいく。
 How to improve? What steps we will take? How do you differentiate yourself as a team member?
How to improve? What steps we will take? How do you differentiate yourself as a team member?
ステップ毎に進めていきます。
まず、基本的な構成を説明します。
〈ステップ1 業務改善とは、スキルは〉 業務改善の基本的な見方、必要なスキルについて
〈ステップ2 改善ポイントを見つけ出すには〉 職場全体の業務の改善点を明確にする分析について
〈ステップ3 改善案を考える〉 改善したい業務を明確にし、業務に適した手法やノウハウについて
〈ステップ4 改善のPDCA〉 実務担当者が改善サイクルを回し、スパイラルアップする管理手法について
基本的な構成につづいて、ここからはステップの説明です。
<ステップ1 業務改善とは、スキルは>
ステップ1-1 業務改善とは何だろう
ステップ1-2 業務改善のための3つの視点
ステップ1-3 業務改善の進め方
ステップ1-4 業務改善に必要なスキル
をチームで検討会を持ち、そして計画をみんなで作り、日々是改善を進めます。 タイムラインは下を参考にしてください。 
ステップ1-1 業務改善の目的
事務効率化、作業ミスの低減、業務成果の向上、業務時間短縮です。業務改善は「業務を今よりよいものにする」こと。
4つのキーワード、
・今より工数(人数*時間)をかけず、同じ成果や結果が得られる?
・ミスの低減……”ミスをする、ミスしてしまう”、のナゼ・ナゼ・ナゼナゼを繰り返す
・業務成果のアップ……業務の成果の品質レベルを高くする。
(職場の文化、雰囲気アップのためチームミーティングの時間を増やす、対話時間を増やす)
・業務時間短縮…”短時間で業務が完了するようにできるか”、を確認する
ポイント:目的を同時に達成しようとしない、計画はone line one line. 目的を絞って業務改善を行う。
チームで話し合い、実行タイムラインを決定する。
ステップ1-2 業務改善の3つの視点
業務改善は、利用しているシステムが使いにくい、使い勝手が悪い、そんなときにシステムをすぐに直す、やりやすくすることをしがちですが、そうではなく、
改善は次の3つ視点で取り組みます。
・やり方の改善…業務で利用する帳票類の改良、手順の確認と改善を、関係者で話しながら進めます。
・スキルアップ……担当者によって同じ業務でもかかる時間が違う、アウトプットのレベルが違うについて、ナゼを考え、教え合い、改善を。担当者のスキルアップにつなげる。
・仕事の適正化……経験が必要な業務に、スキル不足の担当者をアサインしない。適任者かどうかを360度でチェックしアサインする。
計画的なアサインは改善に重要な要素です。
ステップ1-3 業務改善の進め方
業務改善の基本ステップ:
Step 1 対象·目的·目標の明確化:
どの範囲を(what extent, what)、どれだけ(how/how much) 改善したいの?を明確にする、
業務改善にかかわるすべて(with whom)の人と共通の認識を(by when/until when)する。
Step 2 現状分析:
現在の問題は何が、どのように、問題の程度を明確にする。
Step 3 改善案のまとめ:
問題点の解決策や改善目標達成のためのアイデアを出す。アイデアをベースに改善案をまとめる。
Step 4 改善の実施:
改善案を新たな業務としてできる手順を決め必要なツールを開発し、改善を実行する。
ステップ1-4 業務改善に必要な技術(スキル)

・分析技術·改善発想法·改善視点·活動管理技術:
業務改善を進めるときは、技術や視点、その視点・見方の訓練が必要で、効果的な改善を実現出来るようにします。
・現状を把握する分析技術:
現在の業務のやり方とそこの問題点を見える化、定量化、それらが誰にも実態を正しく理解、認識できるようにします。
(共通認識と正しい判断)
・改善アイデアを出すための発想法:
ミーティングを行いアイデアをポストイットに書き出し、業務を改善するためのアイデアを出す技術です、ミーティングKJ法等を使いまとめる
・運営上の定石:
情報の伝達や共有のためのITの活用、効果的な会議のための事前準備、MS Teams、 ZOOM の活用。
・活動の管理技術:
日常業務と改善活動の進捗や成果の管理をしていく。MS Teams, ZOOM の活用。
ブレーンストーミング、ブレーンライティング、KJ法等
・KJ法について、 上野千鶴子2018年『情報生産者になる』ちくま新書を参考にしてください。
KJ法の原理はとてもシンプル。情報をいったん脱文脈化したあとに、再文脈化するだけ。
川喜田二郎先生の言い方を借りれば、五里霧中の情報のなかから、筋道を見つけることをいいます。そのとき二次的に得られた再文脈化こと筋道が、情報加工の生産物になります。KJ法のマニュアルはたくさんありますが、KJ法をマニュアルを使って覚えようなんていうのは、見当違い。畳の上で泳ぎを覚えようというくらい、まちがっています。とにかくやってみて、カラダで覚える、それしかありません。やってみれば経験知として伝達可能で学習可能な、納得できる方法であることがわかるでしょう。ここではわたしが実際に授業で使ってきた上野流のKJ法マニュアルを図表8-1………
Business Improvement work

「改善をやり切るコミュニケーション」と「業務改善憲章(Business Improvement Charter)」
その1.不要な業務の発見。
- 不要な業務は何?
- 実際には廃止してもよい業務が存在する?
- 業務改善は不要な業務を見つけ出すこと. (必須)。
不要な業務の発見し、改善策を議論し、改善策を決定し、実行、成果を出す。
不要な業務を発見する視点:
視点1.
社、事業部、部門の使命(ミッション)と業務目的の視点から、この業務が有効であるか? (社、事業部、部門のミッションに貢献のない業務は不要な業務です)
視点2.
実績帳票・実績データがアウトプットに有効に活用されているか? (活用ないと不要な業務といえます)
視点3.
部門間や担当者間で重複した業務は不要な業務です。
視点4.
チェックや承認が必要以上に履行されているのは必要な業務?
必要以上のチェックや承認は不要な廃止可能な業務
- 部門の業務は、部門のミッションを達成するための業務か
- 部門の業務はミッションとリンクが取れている業務か
(関連性のない業務は、基本的に不要) - アウトプットが有効に活用されているか
(作成した書類やデータが有効に活用されていなければその業務は基本的に不要)
- 部門間、担当者間で重複した業務ではないか
(他の担当者や他部門で、同じことを実施している、する場合は、その 業務削減を検討すること)
職場コミュニケーションの活性化 改善をやり切る
職場単位で、業務計画や業務を実施する時の課題などを常に情報共有する
業務活動は日常の業務遂行で上司と部下や同僚間や他部門とのコミュニケーション不足により、多くのムダ、(ムリ、ムラ)が散見されます。 例えば、
その1.提出された報告書は、依頼した内容と異なる報告書となっていた。
その2.職場のメンバーに周知し依頼が依頼通りに周知されていなく再周知とやり直しが発生した。
ムダは職場関係者間のコミュニケーションのプロセスを確立し実施することで回避されます。
(コミュニケーションのプロセス:
毎日、毎週、定期的に、職場メンバー間で業務のさまざまな課題について報告し、議論し合うことによって、個人間の認識の差異が解消されたり、ひとりで悩んでいたことが解決されたりし、効率的な心の健康が満たされた職場と運用が実現されます)
コミュニケーション不足により発生するロス
| 情報共有不足 | 業務のやり直しロス |
| 誤解 情報不足 計画共有不足 業務方法の指示、相談不足 手順の不明確、相談不足 | 誤解によるミスを犯す。 誤った判断をする。(正しい情報は正しい判断) 納期遅延が発生する 1人で悩んでしまう。 (上司からの助言で効率的) 非効率な手順が発生する。 |
改善計画の実施
1.改善を机の上だけでなく、机上で空論実施ではなく現場で「実施」するには、
- 実務担当者が、自分の業務を改善するというケースがほとんどです。
- しかし担当者は日常的な業務の合間に改善を行う状況が実態です。
2. 改善を最後まで現場でやりきるためには、改善案を一人でまとめ、それを実施に移すことは一般的に担当者の努力に任されています。
3.業務改善は、組織的に、お互いに、チェックし合い、相互啓発しながら推進していくことが必要です。
「業務改善憲章(Business Improvement Charter)」を作成する。
改善の実施計画を策定し、見える化し、改善の実施は、ひとりの担当者だけでなく、部門全員が意識して実行すれば、改善を最後まで現場でやりきることができます。
・”日常業務が忙しくなって、遅れ気味だからアイデアが頂戴したい…”
・”ところで、この改善は計画通り実施できている?”
・”それなら、私が手伝ってあげるよ!”
・この実施項目は具体的にどうしたらよいのかな?
・”その実施項目ならこんなことをすればいいよ”
業務改善への取り組みができるのは、企業理念に「何よりも優先すべきは安全である」と明確に述べられて働く人々がその理念に沿ってビジネス活動をしている。
ここで、経営幹部、中間管理者、管理監督者のリーダーシップ発揮に必要な具体的な行動について復習しましょう。
Safety Management Workshop
経営幹部、中間管理者、管理監督者のリーダーシップ発揮に必要な具体的な行動
組織の意識を高くするには、まずトップが率先垂範することです。 以下の行動を可能とするワークショップを提案します。経営理念、安全理念、ビジョン等を浸透させるためには、 三つの価値があります。
- 「顧客重視」
- 「社会と持続的な関係を維持すること」
- 「創造・革新を続けること」
価値、理念が浸透すればするほど、企業のガバナンス(統制)環境や組織風土は着実に改善され、コンプライアンス(遵法)文化が育まれてきます。
したがってリーダーはリーダーシップを発揮して、経営理念、安全理念、安全ビジョンの浸透に旗を振る必要があります。 そこで、質問をします。あなたは経営理念に基づく安全の理念・ビジョンを自分の言葉で社員、他人に語ることができるますか。
- 経営幹部は理念を自らの言葉で語ること。
- 理念の浸透には4段階があります。
浸透度の低いものから順に
- 「理念の存在を知っている」
- 「理念の内容に共感をする」
- 「難解なハードルを超えるためには理念に基づき考える」
- 「理念の内容を他人に語ることができる」 この最後の行動ができれば理念は深く深く浸透していきます。
理念が浸透しているかどうかは、「幹部はもちろん、管理監督者も組織の理念を他人に語ることができるか」を見れば、浸透の度合はわかります。
理念の内容を他人に語ることができ人は、理念に共感を覚えない人、理念を自分の行動に反映させようとしない人などに比べ、理念を他人に熱く熱く語り伝えることができ、浸透度のレベルは深くなって、社員の心に理念を生き続けさせることが出来ます。
組織風土改革を進めるために幹部、中間管理職、管理監督者は理念を自分なりに理解し納得し、理念を現場に反映するために、Personal Safety Action Planに従って実行します。その実行の経験から自分の言葉で「理念の便益、恩恵、利益、価値、意義、」を部下や同僚に語ることができるようになります。職場の一体感を高めるため、働くチームのみんなのことを考えて一人一人に働きかける人格を磨き、自己満足的状態から進歩していけば、職場のみんな(部下)はリーダーとリーダーシップを高く評価します。
幹部管理者は「何がチームの利益になるかを明確に面談コミュニケーションで明確に示し、双方向のコミュニケーションをする。コンプライアンスに沿った、「誠実に仕事をすることがチーム全員の利益になる」という考え方を明確に示し、幹部が本音でコミットすれば、一体感や忠誠心の醸成ができ、組織の安全パフォーマンスを高めます。経営幹部や管理監督者、職場長は組織の安全取組の一体感を強めるためには、 ①安全活動の優秀賞を発行する、②力不足の人を育てる気持ちで助けていく、③気兼ねなく何でも言える話し合いワークショップを実施する。そして安全意識を高くする。これらが安全の意識付け維持する、向上させる有効な高い手段となります。